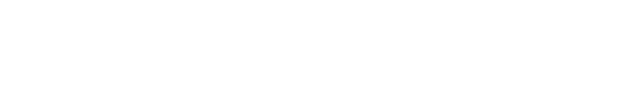マダニ
テレビなどでの報道により、マダニに対して不安を感じている人が少なくないようです。ダニ類は種類の多い虫ですが、昆虫ではなく、クモに近いものです。マダニはダニの仲間で、日本には40種類以上が生息しています。主なものとしては、タカサゴキララマダニ、フタトゲチマダニ、シェルツェマダニ、ヤマトマダニがあります。舌を噛みそうな名前ですね。
どんな虫?
山や林など野外に生息し、ササなどの葉から哺乳類を中心とする野生動物に乗り移って寄生し、血を吸って生活しています。茶色で丸く、成虫でも2~8㎜の大きさですが、たくさん血を吸うと1~2㎝になることがあります。まれに人間に吸着することがあり、重症熱性血小板減少症候群( SFTS severe fever with thrombocytopenia syndrome )や日本紅斑熱、ライム病などの感染症を媒介することから、恐れられています。ただし野生動物のいる地域に住む虫のため、都市部でみられることは、めったにありません。マダニの被害で当院を受診する患者さんの大半は、登山やキャンプなどをした方です。また恐い病原体を持っているのは、マダニの中でもごく一部(1%以下?)とされています。
症状は?
植物の葉などから人間に乗り移ると、衣類や皮膚のうえを歩いて適当な場所まで移動し、頭部の先端にある「くちばし」の様なもの(口器)を皮膚に刺し込んで血を吸うのですが、口器がノコギリ状になっているだけでなく、セメントに似た物質を出して固着させるため、2~3日すると抜けにくくなります。同じ場所で1~2週間(幼虫の場合は数日)血を吸い続けて、お腹がいっぱいになると自然に脱落します。強いアレルギー反応を起こすことは、まずありません。痛みやかゆみが無いため、吸血して大きくなってから気づかれることが多いようです。虫だとは思わず、「丸くて茶色いデキモノが急にできた」といって来院され、話を聞くと「何日か前に、野外レジャーをした」というのが典型的なケースです。
マダニが頭部を皮膚に食い込ませています。4対の脚が見えます。
別の例です。いっぱい血を吸って、大きくなっています。脚は相対的に細く短く見えます。
治療は?
マダニは口器を皮膚に刺して固着させるため、虫を引っ張って取ろうとすると、その口器がちぎれて皮膚の中に残ってしまい、後で炎症を起こすことが少なくありません。一般的な治療は、局所麻酔をして、メスで皮膚ごと虫を切除し、皮膚を糸で縫い合わせることです。小さな手術ですね。吸着して日が浅い場合や、幼虫では、ピンセットなどで取れることがあります。その際は、取った虫をルーペなどで観察し、口器が頭部に残っていることを確認する必要があります。マダニ除去用器具(ティックツイスター®など)が市販されていますが、医療器具ではないため、使用する場合は自己責任でということになります。
頻度は低いのですが、マダニは前述の恐い病原体を持っていることがあります。除去してから1~2週間は、発熱や腹痛、下痢、発疹、出血などがでないか気を付けておく必要があります。疑わしい症状がある場合には、大学病院や、感染症科のある病院(国立国際医療センター 都立駒込病院 など)を受診して頂くことになります。
お役に立ちそうなWebサイトを紹介しておきます。
この項の記載に当たっては、兵庫医科大学の夏秋優 臨床教授の著作(Dr.夏秋の臨床図鑑 虫と皮膚炎 改訂第2版 学研メディカル秀潤社 2023 など)およびご講演の内容を主に参考にしました。夏秋先生に深謝いたします。